2025-07-01、
本日の書籍紹介は、 新しい階級社会 「中流幻想」は、はるか彼方の過去の夢 橋本健二(著)
最近読んだ社会学関連の書籍の中で、橋本健二氏の『新しい階級社会』と小熊英二氏の『日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学』は、社会学を学ぶ上で、重要な書籍です。
『新しい階級社会』は、現代日本が「一億総中流」という神話から脱却し、明確な「階級社会」へと変貌している現状を、解き明かすことに主眼を置いています。
『日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学』は、現代日本の「働き方」や「社会構造」が、歴史的にどのような経緯で形成されてきたのかを、雇用、教育、福祉といった側面から丹念に掘り下げていますので、小熊英二氏の書籍も紹介して、比較してみます。
1.橋本健二氏の『新しい階級社会』の内容
この本は、現代日本が「一億総中流」という神話から脱却し、明確な「階級社会」へと変貌している現状を、データに基づき詳細に解き明かすことに主眼を置いています。
この書籍を読めば、自分の階級が分かります。
<主な特徴・焦点>
■階級分類と実態:
現代日本を「資本家階級」「新中間階級」「正規労働者」「旧中間階級」「アンダークラス」の五つの階級に分類し、それぞれの経済状況、生活実態、意識などをデータで裏付けながら分析します。特に「アンダークラス」という新たな最下層の存在を強調し、その貧困と不安定な生活を浮き彫りにしています。
正規労働者階級とは基本的に異なる階級として「アンダークラス」が登場したことが、新しい階級社会の最大の特徴である。
■橋本氏は、現代日本の階級構造を以下の5つの階級に分けて分析しています。
1)資本家階級 :250万人 (3.9%)
2)新中間階級 :2,051万人 (32.1%)
3)正規労働者階級:1,753万人 (27.4%)
4)アンダークラス:890万人 (13.9%)
5)旧中間階級 :658万人 (10.3%)
■格差の固定化と再生産:
階級間の格差が拡大し、それが固定化され、次世代に継承されている「負の連鎖」を指摘します。
■統計データ中心のアプローチ:
SSM調査など、社会調査の膨大な統計データを駆使し、客観的かつ実証的に日本の階級構造を分析しています。
■現代の課題と提言:
格差拡大がもたらす社会的な弊害を指摘し、格差是正のための具体的な政策提言(累進課税強化、ベーシックインカムなど)や、それを実現するための「弱者」と「リベラル派」の結集の必要性を訴えます。
橋本健二氏の『新しい階級社会』は、日本社会の「今」を深く理解し、未来を考える上で必読の一冊と言えるでしょう。
<目次>
階級構造、それは人生の舞台装置───序に変えて
第一章 「新しい階級社会」とは何か
第二章 「新しい階級社会」が生まれるまで
第三章 五つの階級:それぞれの生い立ちと日常
第四章 哀しみのアンダークラス
第五章 男の階級・女の階級
第六章 人の階級はどうやって決まるか
第七章 階級格差を拡大させた新型コロナ
第八章 格差をめぐる対立の構造と日本の未来
—————————————
本書の骨子となるのは、以下の点です。
1) 「一億総中流」の崩壊と「新しい階級社会」の到来
かつて日本は「一億総中流」と言われる時代がありましたが、これは虚像であり、特に1980年代以降、格差が拡大し、日本は明確な階級社会に突入したと主張しています。
2) 現代日本の五つの階級
橋本氏は、現代日本社会を以下の五つの階級に分類し、それぞれの特徴と実態を詳細に分析しています。
(1)資本家階級: 大企業経営者など、資産を多く持ち、経済的な優位性を持つ層。
(2)新中間階級: 専門職や管理職など、高い教育水準を持ち、安定した収入を得る層。
(3)正規労働者: 安定した雇用形態で働く一般的な労働者層。
(4)旧中間階級: 自営業者や家族従業者など以前は安定していたが近年は厳しい状況に置かれている層。
(5)アンダークラス:
非正規雇用者、パート、派遣労働者など、経済的に困窮し、身分が不安定な最下層の階級。
特に「アンダークラス」という新たな下層階級の存在を明確にし、その置かれた厳しい状況を具体的に示すことで、社会の現状に対する警鐘を鳴らしている点が重要視されています。
特に、ひとり親世帯や未婚の男性に多く見られ、その半数が貧困状態にあり、健康状態や精神的な問題を抱えやすいと指摘されています。
3) 階級の固定化と負の連鎖
本書では、これらの階級間の格差が拡大し、階級が固定化され、貧困の連鎖が次世代へと引き継がれている現状が強調されています。特にアンダークラスは、経済的な困窮だけでなく、ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)も脆弱で、将来への不安に苛まれていると述べています。
4)格差拡大の要因と弊害
格差拡大の要因として、経済構造の変化や雇用の非正規化などを挙げ、この格差が社会全体に弊害をもたらし、排外主義や軍国主義につながる危険性も示唆しています。
5)解決策と行動の呼びかけ
著者は、現在の格差は容認できないほど大きいという立場から、格差を縮小させ、より平等な社会を実現するための解決策を提示しています。その行動の担い手となるのは、「弱者」と「リベラル派」であり、彼らを受け入れる新しい政治勢力の必要性を訴えています。累進課税の強化や資産課税、ベーシックインカムなども解決策として言及されています。
———————————————————————————
特に面白かったのは、第八章 格差をめぐる対立の構図と日本の未来 の章で、「5 新自由主義右翼の正体」で、伝統的な保守の政治的立場に加えて、新自由主義的な自己責任論を振りかざし、格差解消の必要性を否定し、原子力発電を擁護し、戦争を人間の本性による必然と考え、性的マイノリティの承認を拒むという「新自由主義右翼」のユニークさは際立っている。
それでは、「新自由主義右翼」とはどのような人たちなのだろうか?
「新自由主義右翼」は、高学歴かつ高収入で、多くの資産を所有する、主に男性たちで、 自民党支持者の支持率が高く、その支持基盤の中核に位置する。
現代日本の五つの階級で言えば、上位の「資本家階級」であるが、大部分は、従業員規模30人未満の小零細企業の経営者であり、世帯年収はイメージよりも低い1060万円とされています。
この様に、日本社会の岩盤保守と呼ばれている層、階級は、確かに高学歴だが、知性と教養を持ち合わせていない、自分勝手で自分の身の保身が精一杯の「チンケ」な側面を有した人間達であり、大した事のない奴らで、こいつらの意見に従わない方が良いのです。
2.小熊 英二氏の「日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学」の内容
この本は、現代日本の「働き方」や「社会構造」が、歴史的にどのような経緯で形成されてきたのかを、雇用、教育、福祉といった側面から丹念に掘り下げます。
<目次>
第1章 日本社会の「3つの生き方」
第2章 日本の働き方、世界の働き方
第3章 歴史のはたらき
第4章 「日本型雇用」の起源
第5章 慣行の形成
第6章 民主化と「社員の平等」
第7章 高度成長と「学歴」
第8章 「一億総中流」から「新たな二重構造」へ
終章 「社会のしくみ」と「正義」のありか
—————————————————–
<主な特徴・焦点>
■歴史社会学的なアプローチ:
現在の日本社会が抱える問題(労働環境の硬直化、長時間労働、非正規雇用と正社員の格差など)が、戦後日本の歴史の中でいかにして形成されてきたのかを、慣習や制度の成り立ちを解き明かすことで示します。
■「カイシャ」と「ムラ」の分析:
日本社会の基本単位を「カイシャ(職域)」と「ムラ(地域)」として捉え、それぞれの帰属意識や機能が社会構造に与えた影響を分析します。
■「大企業型」「地元型」「残余型」:
現代日本人の生き方を「大企業型」(大企業の正社員として安定したキャリアを築く層)、「地元型」(地域に根差し、自営業や中小企業で働く層)、そして「残余型」(どちらにも属さず、不安定な非正規雇用などで生活する層)に分類し、その形成過程と特徴を明らかにします。特に「残余型」は、橋本氏の「アンダークラス」に通じる概念と言えます。
■慣習(しくみ)の呪縛:
日本社会が歴史的に作り上げてきた「慣習の束」が、人々の行動や社会の変化を規定しているという視点を重視します。
3.2冊を比較して違いと、同じところは
橋本健二氏の『新しい階級社会』と小熊英二氏の『日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学』は、どちらも現代日本社会の構造と課題を深く分析した社会学の重要な著作ですが、アプローチや焦点に違いがあります。
両書籍をまとめると、
橋本健二氏の『新しい階級社会』は「現在、日本社会はどのように分断されているか」を、小熊英二氏の『日本社会のしくみ』は「なぜ日本社会は現在のような分断された『しくみ』になったのか」を、それぞれ異なるアプローチで解き明かす著作と言えます。
両者を併せて読むことで、現代日本社会の構造と、それが形成された歴史的背景をより深く理解することができるでしょう。
1)違い
■アプローチの重心:
・橋本健二:
現在の社会構造(特に階級)を詳細な統計データで「可視化」することに重点を置き、現状の分析と、それに基づく具体的な政策提言が中心です。
・小熊英二:
現在の社会構造が「いかにしてできたか」という歴史的経緯を解き明かすことに重点を置き、現在の「しくみ」が形成された歴史的文脈を理解することで、問題の本質を探ろうとします。
■階級/類型論:
・橋本健二:
「資本家階級」「新中間階級」「正規労働者」「旧中間階級」「アンダークラス」という、より経済的な関係性に基づく「階級」概念を明確に提示しています。
・小熊英二:
「大企業型」「地元型」「残余型」という、人々の生き方や社会への所属形態に基づく「類型」を提示しています。厳密な意味での「階級」とは異なりますが、社会の分断を示す概念として機能します。
■時間軸:
・橋本健二: 主に現代(特に1980年代以降の格差拡大期)のデータを用いて現状を分析します。
・小熊英二: 明治時代以降の歴史的経緯を遡り、現在の社会の「しくみ」がどのように形成されてきたかを解き明かします。
2)同じところ
■「一億総中流」神話の否定:
どちらの著者も、かつての「一億総中流」という日本社会の認識がもはや通用しないことを前提としています。
■社会の分断・格差の認識:
表現は異なりますが、現代日本社会が経済的、社会的に深く分断されており、格差が拡大しているという現状認識は共通しています。
特に、不安定な立場に置かれた人々の存在(橋本氏の「アンダークラス」、小熊氏の「残余型」)に注目しています。
■データと論理に基づく分析:
感情論や思い込みではなく、客観的なデータや歴史的事実に基づき、論理的に分析を進めるという社会学的アプローチは共通しています。
■社会問題への問題意識:
どちらの著作も、現在の社会構造が多くの人々に困難をもたらし、社会全体に弊害を生み出しているという強い問題意識を共有しています。
■「日本的」な社会構造の解明:
欧米社会との比較も踏まえつつ、日本社会独自の雇用慣行、教育システム、福祉制度などが、いかにして現在の社会構造を形作っているかを分析しようとしています。
————————————————————————-
最後に、
たまには、SNS(バカやアホども集合場所)から離れて、書籍を購入して読んでみましょう。そうすれば、脳(頭)の軽さも少しは解消されるでしょうが、数行の文字しか読んでいない輩に、読書を進めても、内容を理解できるかどうか? もうはや、そんなレベルに達しているでしょう。 一億総バカの状態ですか。
—関連記事—
・【書籍紹介】2019年 今年、読んで良かったと思う書籍をまとめてみました。 メインは社会学、脳神経学です。
Sponsored Links

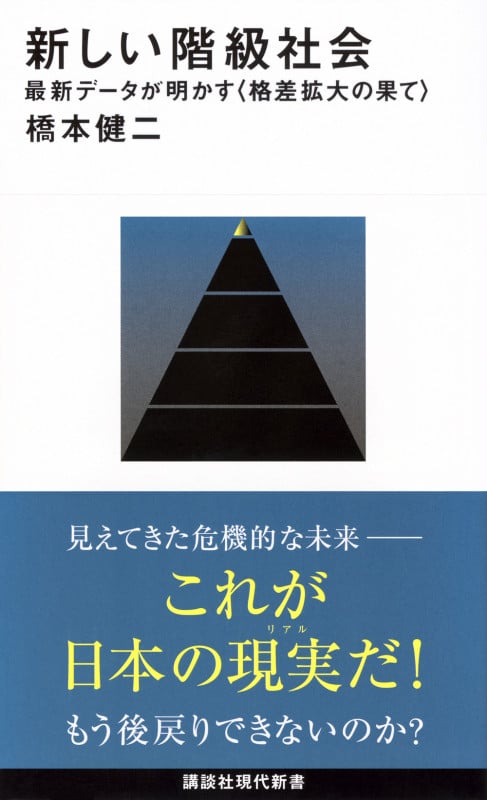
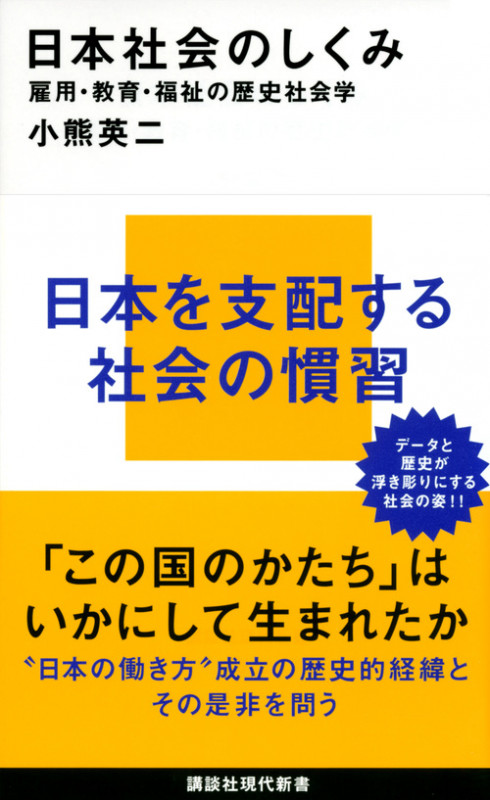
コメント