2025-07-08、
本日の書籍紹介は、戦争はいかに終結したか — 二度の大戦からベトナム、イラクまで 千々和 泰明 (著) です。
『戦争はいかに終結したか』は、戦争の「終わり方」という、ともすれば見過ごされがちな、しかし極めて重要なテーマに焦点を当てた一冊です。
多くの書評で指摘されているように、本書は過去の主要な戦争(第一次・第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク戦争など)を具体的な事例として取り上げ、戦争終結のメカニズムを多角的に分析しています。
<目次>
序章 戦争終結への視角―「紛争原因の根本的解決」と「妥協的和平」のジレンマ
第1章 第一次世界大戦―「勝利なき平和」か、懲罰的和平か
第2章 第二次世界大戦“ヨーロッパ”―無条件降伏政策の貫徹
第3章 第二次世界大戦“アジア太平洋”―「幻想の外交」の悲劇
第4章 朝鮮戦争―「勝利にかわるもの」を求めて
第5章 ベトナム戦争―終幕をひかえた離脱
第6章 湾岸戦争・アフガニスタン戦争・イラク戦争―共存から打倒へ
終章 教訓と出口戦略―日本の安全保障への示唆
———————————————————————————
■まとめ
千々和 泰明さんの『戦争はいかに終結したか』は、戦争の「終わり方」というテーマに独自の視点から切り込み、歴史的な事例を通してそのメカニズムを解明した力作です。
国際政治に関心のある人だけでなく、現代の安全保障問題を考える上で必読の一冊と言えるでしょう。特に、有事の際の日本のあり方を考える上で、示唆に富む内容となっています。
1.戦争はいかに終結したか この書籍を読んでいると、民意で戦争を止めようなんてできない気がするが? どうしてか?
千々和泰明さんの『戦争はいかに終結したか』を読んだ上で、「民意で戦争を止めようなんてできない気がする」という感想を持ってしまいますが、本書の重要な論点の一つを捉えていると言えるでしょう。
なぜ民意だけでは戦争を止めることが難しいと感じられるのか、その理由をいくつか掘り下げてみます。
1)「現在の犠牲」と「将来の危険」のジレンマ
本書が繰り返し強調する「現在の犠牲」と「将来の危険」のジレンマは、「民意」が戦争終結に与える影響の限界を示唆します。
- 「現在の犠牲」への耐性:
戦争が始まると、国家はプロパガンダや情報統制を通じて国民の士気を高め、犠牲への耐性を醸成しようとします。国民感情も高揚し、「国のため」「正義のため」という意識が強まる中で、多少の犠牲は許容される傾向にあります。この段階では、戦争を止めることを主張することは「非国民」と見なされるリスクさえ伴いかねません。 - 「将来の危険」への懸念:
敵国を完全に打倒しない限り、将来再び脅威にさらされるのではないかという「将来の危険」に対する懸念も、民意を戦争継続に傾けさせます。特に、相手国への不信感や過去の経緯がある場合、国民は「今ここで手打ちにすれば、将来もっと大きな犠牲を払うことになる」という思考に陥りやすく、徹底的な勝利を求める声が大きくなります。
このジレンマの中で、たとえ多くの国民が疲弊し、犠牲に苦しんでいても、「将来の危険」を回避するためには戦争を続けるしかない、という選択を支持せざるを得ない状況に追い込まれることがあります。
2)リーダーシップの役割と硬直性
本書の分析からは、戦争終結において指導者の判断が極めて重要であることが示唆されます。
- 指導者の利害:
指導者は、自らの権力維持や歴史的評価を考慮するため、国民の感情や犠牲だけを単純に考慮するわけではありません。戦争を途中でやめることは、敗北を意味する可能性があり、指導者の政治生命を終わらせるかもしれません。このため、国民が疲弊していても、指導者が自身の立場を守るために戦争を継続するという判断を下すことがあります。 - 「損切り」の難しさ:
戦争には莫大なコスト(人的・物的・経済的)が投じられます。途中で戦争を止めることは、これまでの犠牲が無駄になるという感覚(サンクコスト効果)を国民や指導者に与えかねません。「ここまで多くの犠牲を払ったのだから、今さらやめるわけにはいかない」という心理が働き、終結への道を遠ざけます。民意もまた、この「損切り」の難しさに影響されやすいと言えます。
3)情報の非対称性と世論操作
現代社会においても、政府は戦争に関する情報をコントロールし、世論を操作する手段を持っています。
- 情報統制とプロパガンダ:
戦争中は、政府が都合の良い情報のみを公開し、敵国の残虐性や自国の正当性を強調するプロパガンダを積極的に展開します。これにより、国民は客観的な状況判断が難しくなり、政府の描く「勝利」という目標に向かって支持を固めやすくなります。 - メディアの影響:
メディアもまた、戦争遂行を支持する報道に偏ることが多く、国民が多角的な視点から戦争を捉える機会を奪われることがあります。
これらの要因により、たとえ戦争への不満が民衆の中にくすぶっていたとしても、それが組織的な反戦運動や戦争終結を求める声として表面化し、政治的意思決定に影響を与えるまでには、非常に高いハードルが存在します。
4)「勝利」への幻想と「敗北」への恐怖
本書で示されるように、多くの戦争は「勝利」という目標を掲げて始まります。
国民もまた、「必ず勝つ」という幻想や期待を抱きがちです。
- 「敗北」の回避:
戦争を途中で止めることは、多くの場合「敗北」や「不完全な勝利」として受け取られます。これは国民にとって心理的な抵抗感が大きく、国家の威信や名誉に関わる問題として捉えられやすいです。そのため、たとえ実質的に勝ち目のない状況であっても、「敗北」を避けるために戦争継続を支持する傾向があります。
これらの点から、『戦争はいかに終結したか』を読むと、戦争の終結が単なる民意の総意によって決定されるのではなく、指導者の判断、国際政治の力学、そして何よりも「現在の犠牲」と「将来の危険」という冷徹な計算に基づいて行われることが痛感されるのではないでしょうか。
民意は重要な要素ではありますが、それ単独で戦争を止めさせる決定力を持つことは稀であり、むしろ、他の複合的な要因によって形成され、翻弄される側面が強い、という現実を本書は示唆していると言えます。
2.例えば、ウクライナの様にか?
ウクライナの状況は、千々和泰明さんの『戦争はいかに終結したか』で述べられている「民意だけでは戦争を止めにくい」という論点を具体的に示していると言えるでしょう。
ウクライナにおける戦争終結の難しさには、本書の主要な分析枠組みが当てはまります。
1)「現在の犠牲」と「将来の危険」のジレンマ
■ウクライナ側:
確かに甚大な「現在の犠牲」(多数の死傷者、国土の破壊、経済的損失など)を払っています。しかし、ロシアとの間で「将来の危険」を排除するという強い意志があります。つまり、もし今、領土を割譲する形で停戦に応じれば、ロシアが将来再び侵攻してくる可能性が高いという懸念が国民の間で共有されています。そのため、たとえ犠牲が大きくても、「ここで踏みとどまらなければ、国がなくなる」という強い動機が、戦争継続の民意を支えています。
■ロシア側:
ロシアもまた、経済制裁や人的損失という「現在の犠牲」を払っています。しかし、プーチン政権はウクライナをNATOの脅威と見なし、自国の安全保障上の「将来の危険」を排除するためと主張しています。国民の疲弊があるとしても、プロパガンダや情報統制により、この「将来の危険」を強調し、戦争継続を正当化しています。
2)指導者の役割と「損切り」の難しさ
■クライナのゼレンスキー大統領:
国民の強い抵抗の意思を背景に、徹底抗戦の姿勢を崩していません。「領土の回復なくして和平なし」という原則を掲げることは、国民の士気を維持し、国際社会からの支援を引き出す上で極めて重要です。この姿勢は、ロシアからの侵略という圧倒的な**「将来の危険」への対抗**として、国民から強い支持を得ています。
■ロシアのプーチン大統領:
彼の立場からすれば、これまでに投じた莫大な資源や人的損失、そして自身の政治的威信を考えると、「今さら引き下がれない」という「損切り」の難しさが非常に大きいでしょう。明確な「勝利」の形が見えない中で戦争を終わらせることは、彼自身の権力の不安定化に繋がりかねず、民意も操作されやすい状況です。
3)情報統制と国民感情
■ウクライナ:
開かれた情報環境と、ロシアによる侵攻という明確な脅威があるため、国民の抵抗の意思は非常に固く、政府の戦争継続方針への支持は強固です。
■ロシア:
厳格な情報統制とプロパガンダにより、国民は戦争の真の状況や犠牲について正確な情報を得にくい状況にあります。これにより、批判的な民意が形成されにくく、政権の戦争継続方針が維持されやすくなっています。
■結論として
ウクライナの事例を見ると、確かに国民の中には戦争への疲弊や平和を願う声もあるでしょう。
しかし、国家の存立に関わる脅威に直面しているウクライナ、そして自国の安全保障や指導者の威信に固執するロシアという構図の中では、個々の民意が直接的に戦争終結を決定づける力を持つことは非常に難しいことが見て取れます。
むしろ、民意は指導者の戦略や国家の置かれた状況によって形成され、戦争継続の動機付けとして利用される側面が強い、という千々和さんの分析が、ウクライナの現状にも深く当てはまると言えるでしょう。
この状況がどのように、そしていつ終結するのか、本書の視点から注視していく必要があると感じる。
もう一つ、戦争が終わり、日本では敗戦記念日近くに、忘れない様にと、悲惨な映像などが放映されるが、役に立っているだろうか? 民意では戦争は止められないし、終わらせる事さえできないのです。 愚民に何を訴えるべきか、再度考える必要があるでしょう。
これもできなければ、もう終わっています。
—関連記事—
・【書籍紹介】 世界の力関係がわかる本 ――帝国・大戦・核抑止 千々和 泰明(著)
・【書籍紹介】 歴史と戦争 半藤一利 著 昭和十五年の群集心理 人間の「愚かさ」を。
Sponsored Links
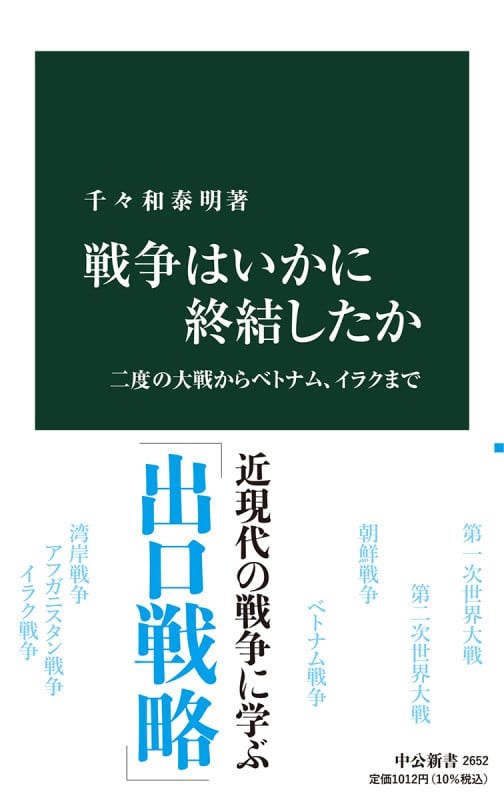
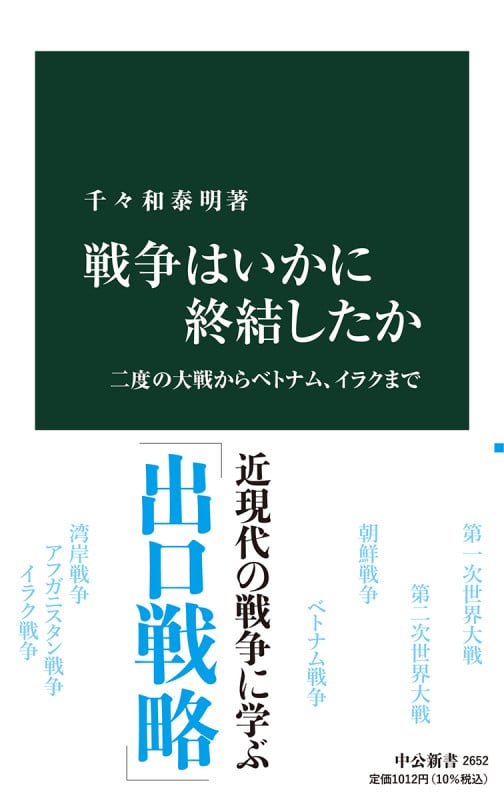
コメント